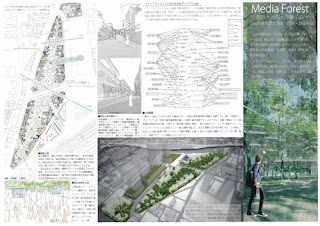北中進 日本大学薬学部教授(薬学博士)のプロフィール
| 72年日本大学理工学部薬学科卒業、74年富山大学院薬学研究科修士課程終了。 |
| 国の厚生科学研究事業の一環である「アレルギー疾患を抑制する天然薬物シジュウムの研究」にも携わった生薬研究のエキスパートで、特にアレルギー作用について造詣が深い。 |
| 87年薬学博士、95年より現職。 |
| 現在は、天然薬物中世生物活性成分などの研究に従事。 |
| 日本生薬学会評議委員、日本薬学会会員、日本免疫学会会員。 |
また、農作業に手間がかからず(?)、一度は荒れてしまった耕作放棄地でも栽培できることが本案件のテーマでもありました。
これらの開発・特許が農商工連携や耕作放棄地対策のお役に立てれば幸いです。
● 中小企業基盤整備機構「農商工連携パーク」
http://j-net21.smrj.go.jp/expand/noshoko/index.html
● 農林水産省「耕作放棄地対策の推進」
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/index.html
◇ 沙棘を原料とした特許開発 特許-1. 沙棘枝から抽出したエキス並びにそれを含む「発ガン抑制剤及び健康食品」
特許-2. 沙棘種子抽出物「アポトーシス誘発、抗アレルギー及び抗炎症作用」
 サジー(沙棘)とは中国やモンゴルで日照り、干ばつ、激しい温度差、乾燥、砂嵐、土壌浸食、不毛地帯などの厳しい自然環境で生息するグミ科の木。
サジー(沙棘)とは中国やモンゴルで日照り、干ばつ、激しい温度差、乾燥、砂嵐、土壌浸食、不毛地帯などの厳しい自然環境で生息するグミ科の木。* 中国では荒地に自生しているようです。* これを原料に様々な商品(健康食品、お茶、菓子類)が考えられ、食品工場と販売会社との連携 が模索できます。 ◇ 桑を原料とした特許開発
 特許-3.クワ科植物による「抗肥満剤及び糖尿病改善剤」 今や、多くの方々が肥満や糖尿病で悩んでいます。その意味では有力候補です。また桑畑は、養蚕業として全国に網羅していた農産物です。農家の人にとって馴染みのあるもので、栽培も楽ではないかと思われます。原料として使われる桑は、根っこ、葉っぱ、小枝と無駄なく使え、その分、開発する商品の枠も広がります。(お茶、健康食品、お菓子など)
特許-3.クワ科植物による「抗肥満剤及び糖尿病改善剤」 今や、多くの方々が肥満や糖尿病で悩んでいます。その意味では有力候補です。また桑畑は、養蚕業として全国に網羅していた農産物です。農家の人にとって馴染みのあるもので、栽培も楽ではないかと思われます。原料として使われる桑は、根っこ、葉っぱ、小枝と無駄なく使え、その分、開発する商品の枠も広がります。(お茶、健康食品、お菓子など) ◇ 植物ネムノキを原料とした特許開発これには、正直驚きました。新しい特許開発です。 特許-4.植物ネムノキによる「抗肥満剤及び糖尿病改善剤」
◇ 植物ネムノキを原料とした特許開発これには、正直驚きました。新しい特許開発です。 特許-4.植物ネムノキによる「抗肥満剤及び糖尿病改善剤」 ご興味のある方は、以下へどうぞ。ご連絡をお待ちしております。
◇ お問合せ先i.tateishi@gmail.com 立石まで * 上記の特許開発1~4は、日本大学から弊社へ技術移転をしております。 (特許使用許諾権取得)